平成30年度活動の歩み
行事案内・ニュースなどです。不明な点がある場合はお問い合わせください。
平成30年度富山ユネスコ協会総会
4月14日(土)13時より、富山電気ビルディング新館6階 北陸電力集会室において、平成30年度の総会を開催しました。
高桑会長を議長に選出後、昨年度の事業報告や今年度の事業計画などについて審議、原案通り承認されました。
今年度は役員の改選が行われ、新会長に高木要志男さん(前副会長)が選出されました。高桑前会長は理事(顧問)として今後も活動に携わられます。
また、高校生2年生の谷山さん(2年生)が、昨年度の学生ユネスコ弁論大会で高校生の部1位となった演題「自ら学び思いを律する」を会員の皆さんに披露しました。
総会終了後は、落語家 三遊亭良薬 師匠による「笑いとコミュニケーション」と題した記念講演が行われました。




第1回会員交流会
第1回会員交流会を、6月9日(土)とやま市民交流館 CiCビルで開催しました。高木会長挨拶の後、引き続き高木会長から「カンボジア寺子屋運動モニタリングツアー報告」が行われ、アンコール寺子屋プロジェクトの概要と訪問した寺子屋の状況を多くの写真をもとに報告されました。
その後、今年度新たに実施を予定している「第1回 ユネスコ教室」について案内書(案)に対する意見交換および日本ユネスコ協会連盟評議員会の議事報告が行われ、予定していた交流題目はすべて終了しました。
「世界遺産相倉合掌造り集落茅場の下草刈り」ボランティア
富山ユネスコ協会では「相倉合掌造り集落茅場の下草刈り」ボランティアを7月22日(日)、同集落保存財団のご協力の下に実施した。
茅場の下草刈りは世界遺産の保全に協力しようと平成17年から毎年この時期に行っており、今回で14回目を数えた。県内各地の会員をはじめ、南砺ユネスコ協会、北陸電力、北陸電気保安協会、一般のボランティアなどから約53人もの参加を得ることが出来た。今年は、猛暑続きで熱中症が心配されたが、水分補給を十分にして、無事乗り切ることができた。40アールの茅場では、カヤが順調に生育し、その中に分け入って、汗しながらカヤに絡んで倒伏の原因になるフジなどのツル植物を刈り取った。
この作業の実施により、合掌造りの伝統建築を守る取り組みの苦労や大切さについて理解を深めることが出来た。
引き続き、研修会を開き、宮本友信氏の「五箇和紙の伝統をひきついで」と題する講話を拝聴した。

「平和の鐘を鳴らそう」キャンペーン
今年は富山市民プラザ アンサンブルホールを主会場として7つのサブ会場において「ユネスコ平和の鐘を鳴らそう運動」を開催しました。以下は各会場の状況です。
1.メイン会場(主催=県ユ連、富山ユ協 共催=日ユ協連、氷見ユ協、南砺ユ協)
| 〇会 場 | 富山市民プラザ アンサンブルホール(会場責任者:浅野) |
| 〇日 時 | 8月1日(水)15時~16時 |
| 〇参加者 | 約180名 |
髙木会長の「混迷と不安定さを増す国内外の状況下で、ユネスコ憲章の人の心の中に平和の砦を築こうという理念は、ますます重要性を増している。平和の鐘を突き、平和を願うみんなの気持ちを世界に向けて鳴り響かせて頂きたい」との挨拶に続き、来賓の富山県教育委員会 渋谷克人教育長(生涯学習・文化財室 菊池政則様 代理出席)、富山市教育委員会 宮口克志教育長様よりご挨拶をいただきました。
続いて、7月に「平和について考える」をテーマとして開催されたユネスコ教室に参加した4名の児童が、それぞれ感想を発表しました。
その後、「富山市民感謝と誓いのつどい」に参加した大広田小学校の約60名の児童を含めた参加者全員で「ユネスコ憲章前文」および「わたしの平和宣言」を唱和し、平和を願って、一人ひとり鐘を鳴らしました。
なお、今年もボランティアとしてユネスコスクールの「中央小・五福小・堀川小・光陽小・富山大附属」から19名の児童・生徒が参加し、パンフレット等の準備や受付、会場整理などを担当してもらいました。
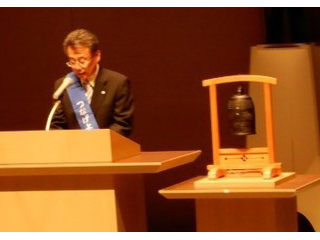





2.サブ会場(富山ユ協主催)
各会場ともユネスコ憲章前文、わたしの平和宣言の唱和を行いました。
| (1) | 会場:常照寺」射水市(旧新湊市)作道 | (会場責任者:澤田理事) |
| 日時:7月21日(土)18:00~ | ||
| 日時:7月22日(日) 6:00~ | 参加人数:35名 | |
| (2) | 会場:「無量寺」射水市(旧新湊市)鏡宮 | (会場責任者:澤田理事) |
| 日時:7月22日(日)15:30~ | 参加人数:21名 | |
| (3) | 会場:「法泉寺」射水市(旧新湊市)久々湊 | (会場責任者:澤田理事) |
| 日時:7月29日(日) 9:15~ | 参加人数:17名 | |
| (4) | 会場:「上行寺」富山市楡原3743 | (会場責任者:水上理事) |
| 日時:7月29日(日)13:00~ | 参加人数:70名 | |
| (5) | 会場:「瑞現寺」射水市(旧新湊市)野村 | (会場責任者:澤田理事) |
| 日時:7月29日(日)17:00~ | 参加人数:53名 | |
| (6) | 会場:日本キリスト教団「二番町教会」富山市一番町 | (会場責任者:野上理事) |
| 日時:8月12日(日)11:45~ | 参加人数:20名 | |
| (7) | 会場:「浄土真宗本願寺派富山別院」(西別院) | (会場責任者:野上理事) |
| 日時:8月15日(水)11:45~ | 参加人数:26 名 |
・法泉寺会場では朝の9時頃より児童たちが三か所の地蔵さんへのお参り(法泉寺と金像寺の各住職による)の後12時頃に法泉寺で鐘を鳴らしました。暑い中辛抱強く参加していたことに感心させられました。瑞現寺では地元のボランティアなど多くの大人の参加ありました。
(澤田理事)
・上行寺会場では髙木会長の講演「カンボジアと寺子屋」の後、中学生から書きそんじハガキ回収の呼びかけを行いました。
(水上副会長)
・西別院では今回は7名もの僧侶の皆さんも参加されいつも以上に活発なものとなった。
(野上理事)
以上 総参加人数: 422名
関係各位のご協力ありがとうざいました。

ユネスコ科学フェスティバルinワンダー・ラボ2018
| 〇実施日 | 平成30年9月22日(金)~24日(月・祝) |
| 〇会 場 | 北陸電力エネルギー科学館「ワンダー・ラボ」(富山市牛島町) |
富山ユネスコ協会と北陸電力エネルギー科学館「ワンダー・ラボ」が共同で「教育、科学、文化」の推進のために平成17年に立ち上げた「ユネスコ科学フェスティバル」イベントも14回目となりました。
今回は富山市内のユネスコスクール(堀川小学校、中央小学校、光陽小学校、五福小学校、楡原中学校)の生徒ボランティア25名および先生方の協力のもと、『子どもたちの未来のために、今できること』をテーマに開催しました。
当日の会場ではLEDを使った「色変わりちょうちん」、モーターを使って動く「UFOバー」など5種類の工作や、手回し発電機を使った実験ゲームを楽しみました。
また、ユネスコブースでは、生徒ボランティアが富山ユネスコ協会の活動クイズを用意し、年齢に応じて正解を教えてあげたり、参加者に「ヒュンヒュンこま」の制作指導をしたりしました。また「平和の鐘」の体験、「募金箱」の協力も実施しました。
初日、水上副会長の開催あいさつに始まったフェスティバルも多くの児童や親子連れで賑わい、各ブースに長い行列ができるほどの大盛況となりました。3日間で1,670名の来館がありました。
(植田 浩平)


第67回学生ユネスコ弁論大会
| 〇実施日 | 平成30年10月6日(土) |
| 〇会 場 | ファーストバンク・キラリホール(TOYAMAキラリ9階) |
高校生の部は4校から9名、中学生の部は10校から13名の参加がありました。
中・高校生ともにユネスコの精神や理念を踏まえ、「世界の平和と戦争」「国際理解」「ボランティア活動」「環境保全活動」、また「地域文化の大切さ」や「心の豊かさ」など様々なテーマについて、自分自身の体験を通して学んだことや考えたことを力強く発表しました。
審査の結果、高校生の部は2年生の高島さん、中学生の部は3年生の牧田さんが1位に選ばれました。高島さんは、「一つの海を守るために」という演題で、人間の生活で出るゴミが海を汚染していると指摘し、アジア全体で環境保全活動に取り組むことや一人一人の小さな心がけが必要であることを訴えました。牧田さんは、「国境を越えて」と題して、幼い頃に住んでいた海外と日本の暮らしを比べ、物の豊かさよりも、心の豊かさを大切にすべきなのではないかと投げかけました。
自分の言葉で熱い思いを込めて語る発表者の強い主張が十分に伝わり、「中学生や高校生が、社会に目を向け、真剣に考えていることに感銘を受けた」など、多くの聴衆の心に感動を残す素晴らしい弁論大会となりました。
(城野 実井子)


2018年度中部西ブロック・ユネスコ活動研究会in南砺
■1日目(11月10日)南砺市福野文化創造センターヘリオス
山辺美嗣会長のご挨拶にもありましたが、2011年に誕生した南砺ユネスコ協会が中部西ブロック研究大会を主管し開催されたことは意義深く、心より敬意を表したいと思います。

大会テーマ「持続可能な社会と環境の実現に向けて今、私たちができること」について考え合い、実行する契機となる大会であり、ESDとSDGsを中心としたプログラムが多様に組まれていました。
日本ユネスコ国内委員の今みどり氏の報告、青年評議員の長坂朋美氏の報告。九州大学国際交流推進室特任教授の浅井孝司氏による基調講演。また、事例発表として、南砺市立福野小学校4年生、富山市立楡原中学校1年生、富山国際大学付属高等学校ユネスコ部、それぞれの児童生徒、越中五箇山菅沼合掌集落保存顕彰会の荒井崇浩氏によるプレゼンがあり、参加者による質問や意見交換がありました。
以下、私自身が印象に残ったことについて述べてみます。

1.基調講演から
ESDとSDGsの具体的な説明があり、「地球市民として私たちが身近にできることは何か」考えさせられる講演でした。
私たちは、SDGs(「誰も置き去りにしない」「よりよい地球をつくるために」2030年までに国際社会が一丸となって取り組むべき事柄を17の目標に定めたもの)の掲げる諸目標達成に向け、ESD(持続可能な開発のための教育)を実践していることになります。
日本ユネスコ協会連盟はもとより私たちユネスコ協会においてこれまでESDを推進してきたのですが、内部外部を問わず話をしていてもすっきりしなかったように思います。それが、SDGsという大目標が近年大体的に広報され施策に採り入れられることによって以前よりわかりやすくなってきたように思います。SDGsの目標4は「質の高い教育をみんなに」です。例えば、ユネスコの世界寺子屋運動を推進する上で、不可欠な活動となっている「書きそんじハガキ回収キャンペーン」は、教育を通じた平和な世界への貢献という意味において私たちには大事な活動なのです。そのことを会員だけが理解しているのではなくて、児童生徒、一般の方に理解し協力してもらう必要があります。
ただし、学校教育でも私たちの活動でも気を付けていきたいことは、SDGsのためにESDがあるという短絡的な認識ではなく、人と人、地域と地域、国と国といった関係性の中ではぐくみ、活動していくものだということです。
2.児童生徒の発表から

福野小学校の4年生は、「夜高祭」「里芋まつり」の歴史、魅力、課題について自分たちで調べたこと、考えたことを発表していました。授業(総合的な学習の時間)で取り組んでいることなのですが、福野での地域行事に素直に向かい合い、自分は(自分たちは)どう取り組みたいのか、明快に発表していたと思います。子どもらしさも大いに発揮していたところに好感をもちました。
楡原中学校の1年生は、神通碧小学校でもユネスコスクールとして活動してきています。それだけに「平和の鐘を鳴らそうin上行寺」「アートマイルプロジェクト」の活動紹介には、平和・国際交流というテーマ性がありました。生徒が中心となって企画・運営し平和について考える活動、絵画制作を通じて他国の生徒と交流する活動です。
ユネスコスクールプロジェクト・ネットワークは、ユネスコスクール憲章に示されたユネスコの理念を実現するための活動を実践する学校の世界的ネットワークです。今後もネットワークを大いに活用されることを期待しています。
■2日目(11月11日)サンキュー ア・ミューホール
1.代表者会議から

短時間での会議でしたが、会則の見直し、会員の獲得、広報、民間ユ協としてのESDへの取り組み、近隣ユ協との連携、教育委員会や大学とユネスコスクールとの関係等について意見がありました。
共通する課題も多くありましたので、次年度開催の石川県では時間をとって考え合う機会をもてればよいと思いました。
2.パワーアップセミナーから
本ユネスコ協会連盟の事業部部長の関口広隆氏から「世界寺子屋運動ってなに、寺子屋運動語り部講座」というテーマでの話がありました。2019年に世界寺子屋運動が30周年を迎えることもあり、基本的な内容から近年の動向までの説明がありました。関口氏は、長年、世界寺子屋運動にかかわってきておられることから、それぞれに興味深いお話を聞くことができたと思います。
都合がつけば今年の9月に開催される「30周年記念大会」に参加し、世界寺子屋運動の今後の取り組み方について見識を深めてきたいと思います。
今回、「ユネスコ寺子屋運動への取り組みから」という話をさせていただきました。2018年3月に「カンボジアモニタリングツアー」に参加させていただいたことをきっかけとして、どのような取り組みをしてきたのか具体事例として発表しました。児童生徒を対象とした「ユネスコ教室」、小学校での講話、地域活動、一般への働きかけです。結論として述べたのは、①私たち自身が学びながら民間ユネスコ運動を続けていくこと、②ターゲット層・ツール・メディア・インパクトを明確にして取り組むこと、③事業や活動等を振り返り、今できそうな(できる)ことから更新すること、以上3点です。
いずれも、カンボジアを訪問し、皆さんと活動を共にしてきて実感したことです。

3. 2019年度開催について
石川県ユネスコ協会の京村会長をはじめ役員の皆さんから、次年度の中部西ブロック・ユネスコ活動研究会は2019年11月9日(土)、10日(日)の両日、金沢市で開催することが報告されました。皆さんと共に参加し、交流・研修したいと思います。
(髙木 要志男)
2018「絵で伝えよう!わたしの町のたからもの」絵画展
| 〇実施日 | 平成30年11月2日(金)~4日(日) |
| 〇会 場 | 北陸電力エネルギー科学館 「ワンダー・ラボ」(富山市牛島町) |

14回目を迎え、県内の小中学校から966点(小学校54校から537点、中学校32校から429点)の応募がありました。最高賞の日本ユネスコ協会連盟会長賞には和田さん(小学校1年)の作品「彫金師のお父さん」=写真右=が選ばれ、261点の作品が入賞しました。
上位入賞者には11月3日(土・祝)、同会場で髙木会長から表彰状が授与されました。会期終了後の11月25日(日)~29日(木)には、会場を射水市小杉展示館に移し、展示紹介しました。
(佐竹 宏文)

第2回ユネスコ教室
| 〇実施日 | 平成30年12月1日 午前 |
| 〇会 場 | 富山市立堀川小学校 |
富山市内ユネスコスクールの小学生25名、中学生3名の参加がありました。教室の内容は、世界寺子屋運動の概要を理解し、パソコンを活用して書きそんじハガキ等の回収をよびかけるリーフレット作りをしました。指導は、会員の深井美和さんです。深井さんは現在、富山市教育センターの勤務ですが、これまで勤務校でもリーフレット作りの指導経験があります。所々で立ち止まりながら活動を進め、一人一人が自分の発想を大事にするワークショップとなりました。
初めに、子供たちはCDの中に保存されているカンボジアの写真から、リーフレットに取り込む写真を選びます。どういう写真を選んだかによって、書きそんじハガキ回収にあたり何を訴えたいのか明らかにします。写真が決まったらキャッチコピーを考えます。
また、リーフレットですから、写真と文字のデザイン、フォントの大きさや色なども考えなければなりません。根気のいる作業が続くのですが、目的が明確で面白さを感じているのか、集中して取り組む様子が見られました。
終了時間の関係から、一人一人リーフレットをプロジェクターで投影し、どういうところを工夫しているのか、全員で見合う時間をとりました。各自がCDに入れて持ち帰り、学校で完成させて活用してもらうことにしました。
パソコンを使ったワークショップであったため、堀川小学校の情報教育室を使わせてもらいました。休日にもかかわらず、便宜を図ってくださったことに感謝申し上げます。
≪感想≫
・ぼくは、今日いろいろなも字やしゃしんをつかってうごかしたのが、たのしかったです。
(神通碧小学校2年)
・ことばを入れるのがたのしかった。パソコンがむずかしかった。でもできたからよかった。
(神通碧小学校2年)
・世界寺子屋運動のことについて、詳しく知ることができてよかったです。いつも書きそんじハガキがどのように使われているのか知らずに出していたので、今度からはカンボジアの子どもたちのことを考えて出したいです。リーフレット作りでは、最後まで作ることはできなかったけど、いろんな工夫をしたりカンボジアの子どもたちのことを考えて作ったりすることができてよかったです。学校で完成させていいリーフレットにしたいです。
(堀川小学校5年)
・世界寺子屋運動のことを、初めて知ることができました。書きそんじハガキ11枚だけで1人の子どもが学校に通うことができるとは知りませんでした。お母さんにも書きそんじハガキを取っておくように伝えたいと思います。 学校のみんなにも伝えて、学校の書きそんじハガキの回収で、たくさんのハガキが集まるといいなあと思います。そして、学校にいけない子どもたちが少しでも早くいなくなってほしいと思いました。
(古沢小学校6年生)
・今日、世界寺子屋運動を学んで、文字が読めることの大切さについて知りました。識字体験をして、文字が読めないと安全なものを飲むことができません。読めないだけで命にかかわることが分かり、学校に通う大切さを学びました。また、学校に通わないと悪じゅんかんになることを知りました。
学校でリーフレットを完成させて、たくさんの人に広めたいです。
(中央小学校6年生)
・僕は、このユネスコ教室に来て学んだことは初めてで、さまざまなことを知ることができたと思います。特に印象に残ったことは、パワーポイントでの書きそんじハガキ募集のリーフレット作りです。パワーポイントをあまり使ったことがなかったのですが、書きそんじハガキの大切さ、大事さを伝えるために一生懸命作ることができました。小学生もよく理解していて、みんなすごくいい作品だったと思います。このユネスコ教室を何回もすることができれば、もっと協力してくれる人が増えると思います。
楡原中学校では書きそんじハガキを募集する予定です。生徒会が中心になってするので、生徒全体がいっぱい持ってきてくれるようにしたいと思います。カンボジアの人々の役に立てるように、小学生のみなさんと協力していきたいと思いました。
(楡原中学校2年生)
・書きそんじハガキの活動については、以前から知っていましたが、自身でリーフレットを作ってみるとやはり感じ方も変わってきて、キャッチコピーもすぐ思い付きました。この教室で学ぶという経験は、私の学校では私しかできておらず、学校に戻って伝えていくべきだと思いました。また、せっかく作ったので、先生に許可をいただけたら、委員会の活動で活用していきたいと思います。
授業以外の学びができるという現在の環境は、とても恵まれたものである」ということは知っていても感謝の気持ちは薄いというのが現状だと思います。また、こうやって感じたことを文字にできるということも恵まれていて幸せなのだということを、学校のみんなに伝えていけたらと思いました。
他校との交流もでき、自分の生きる環境のありがたさも感じられたので、この約2時間半の学びはとても大きかったと思います。まずは、書きそんじハガキの活動を行おうと思います。ありがとうございました。
(富山大学人間発達科学部附属中学校3年生)
(髙木 要志男)
平成30年度第2回会員交流会
| 〇実施日 | 平成30年12月1日(土)14時~17時 |
| 〇会 場 | CiCビル3階学習室1・2・3 |
初めにユネスコの歌を斉唱した後、髙木会長が交流会の概要説明と午前中のユネスコ教室の実施状況を中心に挨拶されました。
次に交流項目の一番目として高岡御車山会館の学芸員、中村知子様から「ユネスコ無形文化遺産 高岡御車山祭」について以下の内容で講演いただきました。
(1) 高岡御車山祭がユネスコ無形文化遺産「山・鉾・屋台行事」の一つであることから「山・鉾・屋台」の定義や登録までの経緯、決定の理由、そして同時登録した33件の概要を説明
(2) 高岡御車山祭行事についての由来、行事の概要・次第について臨場感のある映像を交えて詳しく説明
※なお、高岡御車山会館では体験ブースや説明ブースがありますので、この機会に訪問されてはどうでしょうか!
流項目の二番目「実施事業を振り返って」については各部会長から発表していただきました。
発表では苦労した点やよかった点、お願い等を説明していただき、持ち時間を超えることもあり活発な交流になりました。なお、「書きそんじハガキ回収キャンペーン」キックオフについても部会長から説明されました。
この後、会長から「第46回評議委員会報告」、事務局長から「日本ユネスコ協会連盟からのアンケート回答内容の報告」、事務連絡(北海道地震へのお見舞金について)を行い今回の交流会を無事終了しました。
終了後に例年通り電鉄富山駅ビルエスタ11階の「アルシェフ」において懇親会を開催しました。
(高寺 政守)


SDGs‐ESD富山シンポジウム2018
| 〇実施日 | 平成31年1月26日(土) |
| 〇会 場 | 富山市体育文化センターサブリアリーナ |
富山市が平成30年6月に国の「SDGs未来都市」に選ばれたこともあり、今年度からテーマに「持続可能な開発目標(SDGs)」を加えました。
県内12校のユネスコスクールの子どもたちが、学校や地域社会でどのようなESDを学び、実践をしているかを家族や地域に向けて発表しました。環境問題、地域の自然や文化、国際交流、防災、福祉などの様々な視点からクイズを出したり実物をみせたりしながら発表しました。想定外の質問に対しても堂々と答える子どもたちに大きな成長をみることができました。小中学生、保護者、教育関係者ら約400名が参加しました。
富山ユネスコ協会として、全体会のアピールタイムで定村事務局長が書きそんじハガキ回収キャンペーンの取り組みを紹介し、協力を呼びかけました
また、富山市科学博物館や富山国際大学など8団体による展示発表に交じって、富山ユネスコ協会も活動紹介、ユネスコクイズ、ぶんぶんごま作りを行いました。予想以上の来場者に、クイズ用紙を追加するほどの盛況でした。中学生ボランティアの二人が協力してくれたので、スムーズに対応することができました。
富山県ユネスコ連絡協議会から発表した子どもたちに、新しいデザインのクリアファイルと缶バッジを記念品としてプレゼントしました。本協会の参加者は、松波、高木、定村、水上、城野、牧野でした。
(水上庄子)



「書きそんじハガキ回収」キャンペーン
【協力要請先】
・県下(氷見市、南砺市を除く)の各学校
小学校(165校)、中学校(68校)、高等学校(49校)、特別支援学校(15校)、射水市内幼稚園・保育園(30園)
・北陸電力グループ、北陸電力労働組合、法人会員等
【回収枚数】 20,480 枚(金額換算 約1,030,000円)
他に、募金や切手、テレカなど収集
【支援先】カンボジア、アフガニスタン、ネパール世界寺子屋プロジェクト他(日本ユネスコ協会連盟へ送付)
【至近年の回収実績】
| 年度 |
回収枚数 (枚) |
換算金額 (円) |
| 平成30年度 | 20,480 | 約1,030,00 |
| 平成29年度 | 25,566 | 1,193,464 |
| 平成28年度 | 29,872 | 1,378,368 |
| 平成27年度 | 30,736 | 1,405,410 |
| 平成26年度 | 30,351 | 1,381,573 |
| 平成25年度 | 28,348 | 1,278,640 |
| 平成24年度 | 26,783 | 1,199,361 |
| 平成23年度 | 26,035 | 1,162,900 |
| 平成22年度 | 23,187 | 1,038,933 |
| 平成21年度 | 27,885 | 1,252,294 |
| 平成20年度 | 36,339 | 1,629,589 |
| 平成19年度 | 33,031 | 1,484,841 |
| 平成18年度 | 44,796 | 1,993,791 |
| 平成17年度 | 30,086 | 1,353,870 |
| 平成16年度 | 5,254 | 236,430 |
このキャンペーンは、平成2年(1990年)からスタートしていますが、途中中断して平成16年(2004年)より再開しました。